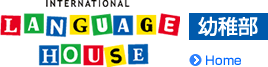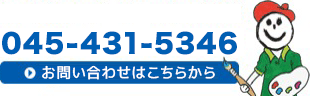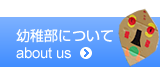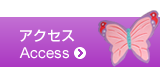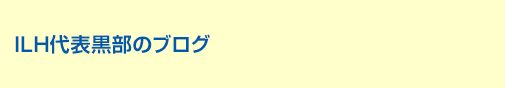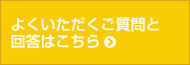ニューヨークに出張した。今回の目的は現地で外国人保育士(英語ではprovider、あるいはcare giverというが、日本語のニュアンスとはちょっと違って,子供のお世話をするという意味合いが強い)と、幼稚園の先生(これは一般にeducatorと言われていて教育者となる)の面接をすること、そして提携先の幼稚園で一日過ごす事、そして今年起動を始めた『ママ笑社」に使える情報収集をすることだった。ランゲージ・ハウスでは来年度に向けて、確実な日本人保育士と外国人保育士のコラボレーション、これには日本で英語講師をしている外国人ではなく、海外の幼稚園で実際に現場で働いている先生を求めている。募集をいろいろな方法で行っているが、最低2年の契約をしたいと思うと、中々人材は見つからない。また日本の子供たちに自分の経験とスキルを通してグローバルな教育をしたいという熱い思いがないと長続きはしない。これらの条件を満たすキャンディデートに出会うのは、宝くじに当たるぐらい難しいこととは思いつつ、あきれめられない。教育はほぼ先生のスキルで決まると思うとなおさらである。今回面接した若手外国人達は、それぞれに日本にあこがれ、日本で働きたいと思っているが、教育者にはまだまだ修行が必要と思わせる者がほとんどで、彼らとは5年後に再会したいと思いつつ契約にはいたらなかった。
幼稚園はRoosevelt Island Pre school という、1.5才から6才まで、つまりキンダーガーデンまでの教育をする幼稚園である。3、4歳児のクラスルームは朝からにぎやかで、思い思いのプレイテーブルで好きな遊びが始まる。1クラスには15人の園児、そして主任教師とアシスタント2人、計3名のプロバイダーが担当する。主任教師はそれぞれのコーナーをくまなく行ききしながら子供たちの様子を見ると同時に、それぞれのコーナーを活用しての幼児教育を行っている。例えば積み木コーナーでは、教師自らクレーン車の真似をして積み木を拾い上げ、それを元あったところへ片付けていく、子供たちも教師の発声するクレーン車さながらの物まねに興味深々、片付け終わるまでに一度も「早く片付けなさい。これをしまいなさい。」などという指示がない。日本の保育士が一日のうち半分以上を、立ちながら仕事をしているのに比べて、それぞれのコーナーに腰を下ろし、子供たちと向き合う姿勢が新鮮だった。子供たちは三々五々教師の膝にきては何やら話しをしていき、また自分の遊びにもどる。教師は子供たち一人一人と丁寧に話している。アシスタントも、それぞれのプレイテーブルで子供たちと会話することを大切にしているようで、その間、ものを片付けたり、次のプログラムへの準備などの慌ただしさがない。いったいどうやってスケジュールが流れているのか不思議なぐらいである。
この園では、9時から12時までhalf dayのプログラムに参加する子供たちと、お弁当を食べてお昼ねをして3時まで遊ぶfull dayとがあるが、圧倒的にhalf dayが多い。理由は料金が高いことと、働く親にとっては3時終了は中途半端で預けにくいこともあるらしい。ニューヨークの働く親たちのほとんどは専属のベビーシッターを雇っていて、大半が掃除、選択、子供への料理などのハウスキーピングもかねている。したがって日本のような保育園はあまり存在しない。地方都市に行くと、いわるゆDay Careといわれる保育所があるが、質のほどはピンキリで、日本の保育園システムのほうが安定また品質もいいように思う。
さて、この幼稚園でバイリンガル教育を専門に研究している教師に出会った。彼女は長年保育士として仕事をしたあと大学に戻り、現在バイリンガル教育の研究をしながらPHD(博士)を目指している。園にもフランス人の子供たちが3名、日本人2名、ブルガリア人1名、アルゼンチン人1名とネイティブの子供達、計15人が英語で過ごしている。最近このフランス人3名が英語に対して、回答拒否を起こしているとか、逆に日本人はお母さんが迎えに来ても日本語で話すことを拒むらしい。ランゲージ・ハウスと同じく、この園でも、英語を一つのコミュニケーションツールとして子供たちの将来に役立つ事を目指し、またニューヨークという社会へとけ込める基盤を作っているが、最近はスペイン語の人口が非常に増加するなか、英語とスペイン語両方を教える学校が増えているという。バイリンガルではない、トライリンガルなアプローチである。私は自分の学校がバイリンガル教育を確率させるための模索を続けているなか、世界は3カ国語を要求するようになる。将来というより、近い現実で日本人ものんびりと構えてはいられなくなる。
空港へ向う帰り、中国系タクシーの運転手の話はまさに現実を象徴しているようでずしりと私に響いて来た。
「僕は高校の時にアメリカに来て大学を卒業しました。英語ができれば仕事にありつける、国際都市ニューヨークで一旗揚げたいと思っていました。ところがみんな英語だけじゃなくてスペイン語、ベトナム語、ブラジル語を話し、英語が話せても、英語で考えられないとまっとうな仕事にはつけないことが解りました。今僕には子供が3人、5年たったら中国に帰る予定です。昔の中国には世界がなかったけれど、今の中国、日本もそうです。それぞれの国の中に世界があります。つまりグローバル社会ということです。なら、こんな物価の高いニューヨークにいるより、子供たちは故郷中国で仕事を見つけて欲しいと思っています。彼らは英語、スペイン語、中国語を話します。無敵ですよ。」
さて、我々日本人はこんな考え方をする中国人に将来本当に対抗できるだろうか。私は思いっきり心配な気持ちで運転手の話を聞いていた。