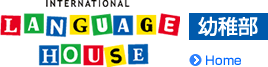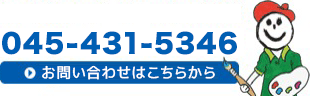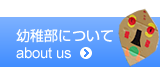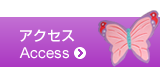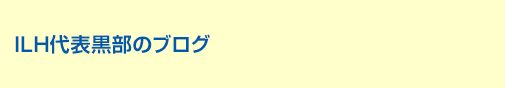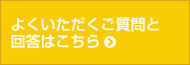卒園児に向けて
あっという間に3月になり、卒園式が行われる3月19日まであと2週間と少し、土日を入れなければの残りは12日である。早い、早すぎると毎年3月になると卒園児たちが愛おしくなる。それにしても子供達の成長は早い。これが一番よくわかるのは子供達が階段を上り下りするときに見える素足の大きさだ。年少から年中の半ばぐらいまでは小さな可愛いベイビーフットが、年中の夏休みを過ぎるあたりから俄然大きくなる。足だけ見ていると幼児ではなく児童といったほうがいい。それほどに足は子供の成長をはっきりと垣間見ることができる。
さて、卒園児に送るメッセージを書きたい。小学校に上がっても忘れて欲しくないことがいくつかある。それはランゲージで培った人間性に関わることがほとんどである。
その1)常に自分に自信を持って闊達に新しい友達や先生と接すること。
小学校に入ると新しい環境のせいか、突然のようにしぼんでしまう子供がいる。
幼稚園ではあんなに意気揚々としていたのに、と親は心配するのだが、子供達とっても新しい環境で自信満々に振る舞うのは大変なことである。4月5月は子供を叱らずにできる限り褒めてあげて欲しい。「すごいじゃん!」と声をかけて欲しい。間違っても「どうしたの?元気ないね、しっかりしなさいよ」とは言わないこと。子供にもプライドがある。
その2)わからないことは解らないということ。解りません、教えてください。
を習慣とすること。
子供に自信がないと、質問をすることが怖くなる。こんな質問をして笑われるんじゃないか、バカだと思われるんじゃないかと悩む子供は多い。しかしこの時期に人に聞いて解らないことを解決するという習慣は大人になってからもずっと役に立つ。反対にこの時期に解らないのにわかったフリをする癖がつくと人生でなんども躓いてしまう。例えば夕食の時、ママは「今日1日何か解らないことがあったら教えてあげる。」というように切り出して守るのも一つである。
その3)困っている人、いじめられている人、弱い人を助ける気持ちを持ち
行動する。
小学校に入るともっと身近にいじめの現場に遭遇するかもしれない。不運にも自分がいじめられてしまうかもしれない。その時は黙っていてはいけないことを教えよう。昔の子供達は言いつけ魔というのがいて、結構活躍してくれた。誰かがいじめられていると、言いつけ魔が先生の所に飛んでいき報告する。それも先生が動いてくれるまでしつこく言い続けてくれる。今はどちらかというと触らぬ神に祟りなしという子供が多いと聞く。また1人で行動する勇気を持たない子が多いので、自分が正しいと思った行動は勇気を持って行うことを教えたい。
その4)英語が理解できればゲームはもっと楽しいし、もっとすごいことができることを教えて欲しい。
英語が話せたり、読めたり、書けたりすることのメリットを子供目線で理解させてあげることが大切である。子供達が今大切にしていることや、面白いことが英語によってより面白くワクワクできることを具体的に教えてあげることで英語への興味は具体的になる。幼稚園や保育園で5年、あるいは4年近く学習した英語には子供達の努力が詰まっている。これを小学校に入ってから継続ができないと数ヶ月で0に戻る。この恐ろしい現実はたくさんの卒園児が体験していると思う。少なくとも子供達の努力を無駄にしないためにも、英語継続の環境を与えるのは親の役目だと考える。
その5)子供の能力があらゆる意味で開発されるのは「遊び」である。
子供達は習い事が増えるたびに笑顔が消えていくという現実を親は真摯に受け止めなければならない。何のための習い事なのか、習い事の目的は何なのかを
家族で話し合って欲しい。情操教育、感性強化、体力増強、運動能力強化と目的はあるかもしれないが、このうちのいくつかは「遊び」の中で解決できることはある。それも子供にとってノーストレスである。子供にとって「遊び」は心身ともに特効薬になることは間違いない。
子供達の未来は無限である。ところが成長するに従って無限は有限になり、時として無だけになる。少なくとも将来、子供達が自分にあった仕事を探すまでは
可能性を無限大にする環境を提供するのは親の役目だと思う。そのファーストステップとしての小学校、この先の6年間を見据えた子育てプランを立ててみてはどうだろうか。
カテゴリ: お知らせ