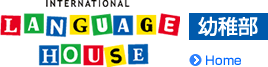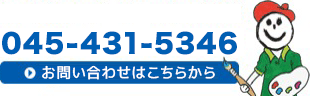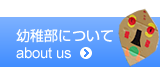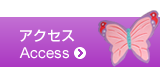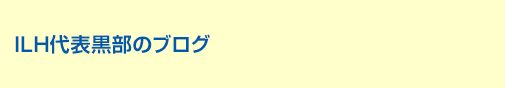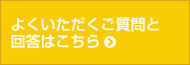どうして英語に出会ったか
よく「黒部さんはどうして英語が好きになったのですか」と聞かれる。残念ながら英語を勉強の一つだとすると好きになったことはない。私は英語に出会った時から、この言葉が話せれば世界をもっと知ることができると信じていた。
英語に出会ったのは3歳の時に通っていた米軍キャンプのバレエクラスだった。先生は日本人だったが、生徒のほとんどがアメリカ人だった。「わあっ、お人形さんと同じ髪の色をしている!目の色が違う!」と子供心に外国人に対する憧れの気持ちが芽生えた。その子たちのそばに行くと金髪でふわふわの髪がサテンのリボンで結ばれ、そのピンク色は今までに見たことのない外国の色、着ているレオタードもピンクで、私にとっては絵本の中に紛れ込んだような不思議な感覚があった。その時は英語?という言語の意味さえ知らなかったが、少女たちへの憧れは、私も同じ言葉で話したいという気持ちに変わった。
その後小学生になってビートルズに出会った。といっても彼らの曲と歌詞である。あまりヒットしなかったが”The Fool on the hill”という曲がある。直訳すると「丘の上にいる馬鹿」となるが、メロディーが良かったので何回も聞いていた。そうしているうちにこの男は馬鹿ではないんじゃないかと思うようになった。当時高校生だった従姉妹が英語好きでそのことを質問したところFoolという意味は愚か者、笑い者、瞑想している人、意識のない人などいろいろあり、この曲の場合は他人からは馬鹿に見えても、本当は真実を知っている者というニュアンスが正しいのではないかと話された。確かにSee the sun going down
And the eyes in his head, See the world spinning aroundという歌詞を見ると実は真実を見抜いている男とも理解できる。もちろんそう理解したのは私自身が高校生になってからだが。
中学生になり英語が書けるようになると、当時流行ったペンフレンドを探し求めた。貿易商を営む叔父がフィリピンの女学生を紹介してくれた。その時叔父がくれた英語の手紙の書き方という本は今でも大切に使っている。クリスマスカードやお礼文などに使う単語が実に綺麗で品がある。多分今では使われなくなった単語もあるかもしれないが、イギリス人にカードを送る時は必ず参考にしている。中学時代はもう一つミュージカル映画が英語学習の起爆剤になった。
The Sound of musicやWest side storyはセリフが覚えられるほどよく見に言った。特にWest side storyはニューヨークアクセントの強いセリフ、スパニッシュ訛りのセリフなど、今まで触れたことのなかった英語の世界を知り、気がつくと少し英語が話せるようになっていた。
高校時代は英語氷河期だった。英語を教える日本人教師の文法攻めにあい、英語そのものの興味を失った。句や節など私にとってはどうでもよかった。一体こんな勉強を誰が考えたのかわからないが、将来言語学者になる以外は役に立ちそうもないので勉強をする気にもならなかった。結果英語の成績はひどいものだった。酷い者だったが、英語を話すという興味だけは失せてはいなかたので、友人と帝国ホテルのロビーに座って外国人をナンパしたり、国際貿易コンベンションなどを見つけては出かけて言った。ある時晴海で行われたアメリカンフェスタに行ったら本物のNative Americanが踊っていた。アメリカンフードのプロモーションだった。缶詰やクッキーなど色とりどりのディスプレイと英語の文字に圧倒された。日本の鮭缶やコンビーフ缶とは違って見たからに美味しそうだった。(実際には日本の缶詰の方が美味しいのだが)私は缶詰に英語で書かれたレベルの内容を知りたくて一つ購入するとしばらくそれが英語の教材となった。
大学になって打ちのめされた。同じ年でこんなに英語の話せる人たちがいるということだった。クラスの三分の一が帰国子女、そしてミッションスクール出身という小学校から12年間私が受けた英語教育の何倍もの量をこなしていて英語が身体中に充満しているかのようだった。この先4年間一体どうやってこの人たちとクラスを共にしていくかを考えると絶望的な気持ちになった。特に帰国子女達の発音があまりに外国人で顔も日本人なのにどこか違って見えた。
それでも何とか卒業できたのはこの帰国子女達のおかげである。日本語がよろしくない彼女達と試験やレポートでGive and takeの協定を結んだ。結果はまずまずであった。ときには出席の返事までしてくれる良き友には今でも感謝している。彼女達と話しているとちょっと外国にいるような気分になることもあり、英語はさておいて海外生活への憧れが芽生えたのもこの頃かもしれない。
就職活動は英語抜きで行った。なぜか。当時英語を使った女性の仕事といえば商社が主流だった。しかし学生時代の成績がそこそこでは到底超えられないハードルだった。負け惜しみではないが商社には興味もなかった。元来事務仕事が嫌いで30分デスクに向かっていると吐きそうになる。まして一日中オフィスで過ごすなどもってのほかである。キャビンアテンダントも多少憧れはしたが試験がかなり難しいと聞いていたので辞退?させていただいた。結局シンクタンクに入社したが、辞めるときに「久保さんはあの大学出ているのに驚くほど英語ができないんだね。」と言われた。真実である。
それでも私のどこかで海外への憧れは大きくなっていた。仕事を1年半でやめフリーターとしてインチキな翻訳や通訳をやった。インチキというと誤解されるかもしれないが、要するにプロではなかった。しかし英語のニュアンスを取るのは得意で外国人には重宝された。サイマル社からきた女性通訳にあなたの英語はかなりやばいと言われていたが。あちらは時給1万円(当時でさえである)こちらは¥1000だから言われても仕方がない。ただ外国人と一緒に話しているのが楽しかった。
結婚して1年目で海外での生活が始まった。運よくNYという街に住むことになり、そこで英語の楽しさを体から感じていた。なぜならそこに住む人はコミュニケーションを何よりも大切なものとし、それが生活の糧にもなっていた。
「楽しい生活を送りたかったら英語で隣人に声をかけてごらんなさい。そこから全てが始まります。」と教えてくれた人たち、このエッセイのタイトルである「どうして英語に出会ったか?」は「人に出会ったから」と簡単な答えで締めくくる。
カテゴリ: お知らせ