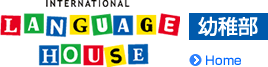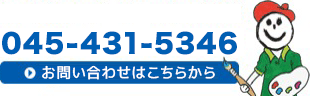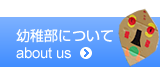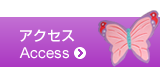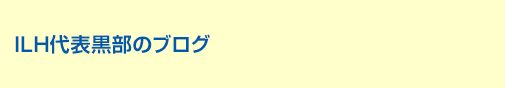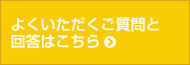拘束された日本人の英語力
日本人拘束と英語力
黒部さん家の教育事情の別記事として、拘束された時の英語力が生死を分けるかもしれないということについて話す。
内線中のシリアで日本人男性が過激派に拘束されたニュースが流れた。
映像の中で男性は過激派の質問にこう答えていた。
過激派:what is your name?
男:My name is Yukawa
過激派:What are you doing here?
男:job, this is job
過激派:Why you carry a gun?
男: Job ここで映像は切れる。
今日本政府はこの男性を救出するために外交交渉をしているが、運良く助かったら、この男性にはもう一度危険回避のための英語を勉強しなおしてもらいたい。なぜなら今回彼の使った英語は、相手に誤解をあたえ、不信感を与えるからだ。
まず、JOBという言葉。これには多くの意味がある。男性は自分が写真家であることを指してJOBといっているのだけれど、ここはtouristといって逃れるべきだった。私も出張の際はtouristを使う。もちろん長期滞在の場合は別だが、
1週間ほどの出張であればtouristが安全圏である。Businessになると通関の時に質問攻めにあい、答えられなければいつまでたっても通関できない。また
時には相手クライアントに連絡がいき、たかが入国のことで迷惑がかかる。
過激派にとって男性のいうJOBはたくさんの仕事を想像してしまう。スパイ、武器販売、国際警察、まして銃を持っているのだから当然のことながらWHY?と聞かれる。Touristであれば、銃を持っていてもFor protectionとか言っておけばいい。個人の護身のために銃を持つのはめずらしいことではない。
報道によると、男性は武装戦線が通りすぎた村を撮影したいと、現地の関係者が止めるのを振り切って行動したらしい。人騒がせな話である。おまけにこの会話力。英語はニュアンスに応じた使い方を知らないと命取りになることだけは肝に命じてほしい。
カテゴリ: お知らせ