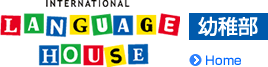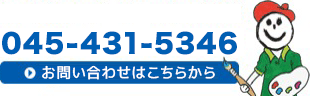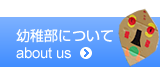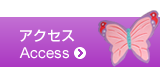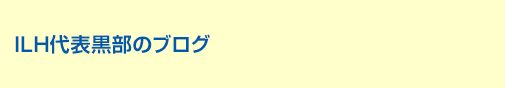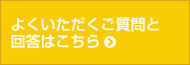英語を小学校の正式教科にする?という記事
7月27日朝日新聞の読者とつくる欄で、英語を小学校の正式教科にする?という記事があった。
小学生英語は11年度から5、6年生で週1コマになった。がしかし、正式教科ではないので成績評価もない。これを先頃、政府の教育再生実行会議がコマ数の引き上げと、開始年齢の引き下げを提言した。あくまでも提言で、具体的に何がどう実行されるのかが解らないのが行政。では小学校の英語学習現場はどうなっているのだろうか。
私も直接現場を見ている訳ではないので、ここは小学生を持つ保護者の方々からの話をまとめてみた。
○ 週1回では何にもならない。英語塾に通っている子との格差が増すだけ。
○ きちんとした年間プログラムの中で英語を教えられる教員が確保できていない。
○ 外国人は以前お客様で、国際理解クラスは直接英語学習には結びつかない。
○ ちょっと話せる子供は先生に逆ににらまれる。
など、など、あまりうれしい話は聞かない。私も以前横浜市教育委員会に体育の時間に英語を導入しませんかと持ちかけて、スポーツ課に回された。少なくとも体育の時間に英語を導入すれば、居眠りして講義を聞く生徒が減るかもしれないと思っただけなのだが。その時に感じたのは、行政の方々にとって、横浜市の小学生が英語を話せるようになろうとなかろうと大した問題ではないということだった。本当に子供たちの将来を思うのであれば、6、3、3の英語学習プランが自然とできそうなものだが、英語学習の内容は1960年代とさほど変わっていないのが現状である。(変わったと思う人はテキストブックの色彩と紙質トリックに影響されたのかもしれない。)
今回の教育再生実行会議も、現状をしっかりと見据えて、長期プランをたてなければ、アジアで一番英語のだめな国日本が簡単に出来上がってしまう。こうなってはグローバル化に対応した教育などというにはほど遠い環境で、いつまでたっても日本人がグローバル社会の中で貧乏くじを引き続けることになる。本気になって日本の英語教育を考え、実行してくれる政治家はでてきてくれるのだろうか。
カテゴリ: お知らせ